勉強は楽しいですか?

でも大人になってからの勉強は楽しむことができます。
森博嗣さんの本『勉強の価値』
をご紹介します。
この本を読むことで、
- 子どもの時の勉強と違う大人の勉強の意義
- 人生がもっと楽しくなるきっかけ
- 人間らしさの価値
を知ることができます。
受け身の時よりも日常の出来事がもっと楽しく生き生きしたものに感じることができるかもしれません。

でもどうせ一度きりの人生を楽しく過ごしたいですよね。

著者のプロフィール

著者:森 博嗣(もり ひろし)
小説家、工学博士。
名古屋大学工学部建築学科卒。
元名古屋大学助教授。

あくまでも仕事や小説は鉄道を作るためという目的だったそうです。
受賞歴(Wikipediaより)
- 1989年 日本建築学会奨励賞
- 1990年 日本コンクリート工学協会賞
- 1988年 セメント協会論文賞
- 1990年 日本材料学会論文賞
- 1989年 日本建築学会東海賞
と仕事上もたくさんの賞をもらいつつ、350冊以上!の小説をはじめとした著書があります。
大学で研究とともに教育に携わり、多くの就職していく学生に関わり、勉強の意義を考えてきた経験やそこで得られた持論を知ることができる本だと思います。

この他に
テレビドラマでも、「すべてがFになる」というフジテレビの武井咲さん、綾野剛さんが主演するドラマの原作も書いています。
本の概要

勉強すべきだし、勉強は楽しい。
- ただし自分の目的・願望を持っていて、それをかなえるための勉強であれば。
目的もなく勉強するのは苦行以外の何物でもない。
- つまり子どもの時の義務教育は楽しくない。
大人の勉強
人生経験を積んで大人になるころにようやく、自分自身の目的や夢を持つようになります。
「自分の目標や夢をもてば」それに向かって勉強することは楽しい。
子どもの勉強
義務教育時代の子どもは基本的に人生経験が十分でないために、まだ自分の目的・願望を持っていません。
目的もなく勉強しても楽しくないのは明らかでしょう。
例えば
「世界のあちこちに行って、観光したり現地の人と話をしたい」
というはっきりとした目的や夢があれば、英語の勉強をするのは必要ですし、楽しくなるでしょう。
- 「税関職員と英語でやりとり」
- 「海外で買い物するときの英語のやりとり」
- 「海外で自分の希望を相手に伝える」
など実際に英語を使う場面を想像できます。
でもそんな気持ちもなく、英語の文法を覚えたり、将来使うかわからないような英単語を覚えたりするのは苦行以外の何物でもありません。
つまり目的を持っていない義務教育を受ける年代の子どもに勉強してもらうというのは、子どもにとっては苦行であり楽しくないこと。
そうであっても、
それを自覚つつ、勉強することで、
- 将来にいだく夢の幅が広がる
- 目的を達成するための基礎学力を備える
という基礎体力を身に着けることができます。
義務教育の役割
義務教育を受ける年代の子どもの勉強が楽しくないとして、義務教育の意味は何でしょうか?
それは
- 自分で学ぶための方法を教えること。
- 将来の可能性を広げるために基礎体力をつけること。
その他に集団生活、社会性、協調性がどんなものかを学ぶことも大きな要素でしょう。
他の人と比較して自分の立ち位置や特徴を知るなど世間を知ることができます。
例えば、
- 周囲の人々の才能・性格、家庭環境
- 集団の中での自分の立ち位置
ただし、集団生活に合わないという個性も大事にすべきでしょうし、勉強しなくても生きていけます。
多様性がもっと重んじられるべきで、画一的な個性に無理にならないように注意が必要でしょう。
勉強自体については、
義務教育では
- どれだけ覚えたか
- どれだけ知っているか
が問われます。
この記憶・知識を持つことは子ども時代に、集団の中で比較される物差しになるのは事実ですが、今の時代にはPCで代替できることです。
もっと大事なことは
- 発想力。
- そして人間として大事なことは自分なりの考えを持つこと。
勉強になったポイント

人間たるゆえん
いわゆる「物知り」という記憶や知識を持っているということは今の時代には重要ではありません。
- PCがあれば代用できることだからです。
むしろ、
- 自分なりの考えを持つこと
- 発想力をつけること
といった、人間だからこそできる力を身に着けることが本質的であり、価値が高いと言えます。

問題を解決するのではなく発見する
学生時代の特徴は、試験でも
- 問題を解く
という能力が問われます。
- 既に問題が提起されています。
- それにその問題に対して答えが用意されています。
実社会ではそんなことがあてはまるのは資格試験程度で、
問題が何なのか突き止める・考える
ということの方が大切です。

持論を持つ
持論を持つ
ということを大切にしたいと思っています。
物事に対する知識を持つことも大事ですがそれ以上に、その物事をどう考えるか、自分だったらどうするかを考えること。

そして人それぞれ違った持論を持つと、いろんな個性をもつ人が増えます。
- 一様な考えの人が集まった社会ではなく、いろんな考えの人が集まった社会ができます。
- 似たり寄ったりの人が集まった社会よりも、多様性をもつ社会の方からは意義のある面白いものが生まれやすい気がしています。
- そんな動きや変化から、また新しいものが生まれるきっかけになりますし、伸びしろが大きいと思っています。
森博嗣さんの他の作品
さいごに
森博嗣さんの本『勉強の価値』をご紹介しました。
勉強というと学生時代の勉強をまず思い浮かべてしまいます。
勉強はある程度の経験や基礎体力を身に着けた大人になってからが本番です。
教えてもらうという受け身の勉強ではなく、目的意識を持って自問自答して今度こそ勉強を楽しみたいですね。

AIやロボットではなく、
わたしたちは「人間だもの」
と普通に言えるように日ごろから心がけたいと思っています。
この記事がみなさんに少しでもお役に立てるとうれしいです。
-

-
【人間力】人間だから集中しません!『集中力はいらない』【書評#20】
続きを見る
-
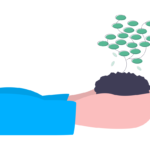
-
自分が夢中になれるものを見つけたくなる本『お金の減らし方』【書評その9】
続きを見る

